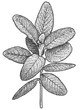バッハ LPレコード100枚との再会(2)マタイ受難曲 (2020.07.26)
■従兄からのメール
サイトを公開したら、まもなく従兄のKENJI君からメールが寄せられた。彼はチェロを奥さんのピアノで共演する音楽愛好家である。バッハにも関心を強く持ち、特にマタイ受難曲が好きとのこと。その刺激を受けて、あらためて、マタイ受難曲(BWV244)を聞くことにした。
■マタイ受難曲は全集100枚組の最初に収められている。4枚で4時間近く。購入当時は実によく聴いた。しかし、当時は旋律を楽しんだり、合唱やアリアの声の美しさを楽しんでいた。時間ができた今回は日本語に訳された歌詞をドイツ語との対訳で読みながら聴くことにした。
マタイ受難曲は、新約聖書マタイ伝のうち26章と27章に基づいている。歌詞は、磔にされて亡くなったイエスキリストの姿から始まり、回想形式で、ユダの裏切り、最後の晩餐、イエスの捕縛、ペテロの嘘、裁判、ゴルゴタの丘へと行く姿などがひもとかれてゆく。
今更ながらの発見があった。曲の中では、歌詞の言葉の一言や一行が楽曲に緻密に編み込まれ繰り返し登場する。歌詞を文字で読んでいるうちは気がつかないポイントだ。教会で受難曲を聴く参集者は、美しい旋律のなかで繰り返される歌詞の一節や言葉を通して、マタイ伝への理解を進めたり共感しながら、イエスキリストの最期を看取ることになる。受難曲はオーケストラとオルガン、合唱団をもとに、コラール(合唱)、アリア、レチタティーヴォ(物語の進行役が歌う歌)などで構成されている。とにかく美しい音色と歌詞が繰り返し反芻されるので聴き手は、イエスの最期の物語が耳に残る。また歌詞がドイツ語なので人々には自然に受け入れられたことだろう。
この曲は、1729年春にケーテンの聖トマス教会で演奏された。バッハ44歳。(初演の場所・時については異論もある。)旋律や合唱はイエスを美しく歌い上げて宗教や国を越えて胸打つ一方で、歌詞の苛烈な描写の組み合わせにはキリスト教の、アンビバレンツなともいえる別の深さをもっていると思われる。

バッハ LPレコード100枚との再会(1)クリスマスオラトリオ (2019.12.25)
押入れ深くにしまっていたバッハの100枚組のLPレコード全集をとりだす。これはもう45年ほど前に購入したアルヒーフ製のもの。当時、会社員になって数年目の地方勤務。給料の3倍近くの値段だったが思い切って購入した。毎晩のように楽しんだ。その後、転勤を繰り返したため持ってゆけず何十年も田舎の倉に置いて来た。その後ひきとったが、変形とカビが心配だった。幸いカビからは免れていた。しかし古い録音なので、さて今はどのように聞こえるのだろう。
ちょうどクリスマス。そこで「クリスマスオラトリオ」と「教会カンタータ」を聴くことにした。
クリスマスオラトリオは、イエスキリストの生誕の物語を福音書を素材にひもといたもの。それを物語る男女の独唱と,合唱,管弦楽で構成されている。バッハはこの曲を、1734年末頃に作曲した。そして、クリスマスシーズンに教会の儀式に合わせて演奏された。当時のドイツの人々は、年に一度あらためてこの楽曲を教会で聴きながらイエスキリスト生誕について思いをしたのだろうと思う。
さて、私はキリスト教徒ではない。歌詞はドイツ語でその言葉に不案内な自分にはわからない。語弊があるかも知れないが、仏教のありがたいお経を聞いている感じもする。
(もちろん翻訳では読んで中身は把握しています。そしてその歌詞が礼賛しすぎであるという批評も仄聞しています。)
しかし、言葉の意味については重要な事ではない。目的は独唱する男女の声を堪能し、合唱の美しさ、そして管弦楽の音を楽しむ事なのだ。おそらく、当時のドイツの人々も教会に響く音を鑑賞することだったのではないかと想像する。
レコードは思いがけなくふくよかな音がした。そして雑音が殆どないことに驚いた。
レコードプレーヤーはPIONEERのダイレクトドライブだ。これも40年以上前のもので会社の先輩から譲り受けた。久しぶりに電源をいれた所、ストロボの橙色の点滅の中でサーボモーターがしっかりと動いている。白色電球のやわらかな光の中で回転するレコードとプレイヤーを見ながら、レコードの音を聞くと、アナログ技術にかけた人々の熱意と出来上がった物が生み出す官能性につくづくと感じ入る。
近年、音楽はPCを使いネットワーク経由で聴いたり購入することが多くなった。しかし、だから、レコードも手放せない。
ベートーベン 交響曲第8番 第2楽章
もう65年以上も前の事だ。家の2階の薄暗い屋根裏部屋には手回しの蓄音機があり、その周りにおびただしい数のSPレコードがあった。父が集めたものだ。わけもわからない4歳の自分はゼンマイ仕掛けの蓄音機のハンドルをくりくりまわしながら手当たりしだいにそれらのレコードを聴いた。鉄針や竹針を使ったことを記憶している。クラシック音楽が主だったが、中にはラジオ体操第一もあった。
そのレコードの一枚に、ベートーベンの交響曲第8番があった。その第2楽章が気に入って繰り返し繰り返し聴くことになった。何度も何度もなのだ。ハンドルをくりくりくり…。なぜ、明るくダイナミックな第1楽章でも3楽章や4楽章ではなかったのだろう。今思えば、弦とともにファゴットが4拍子の軽快なリズムを刻み、それをベースにメロディーが転調されながら次々に展開される2楽章は幼児にはとても魅力的だったのではないかと思う。幼児は繰り返しを好む。蓄音機からかすかに聞こえた2楽章の音色が今も耳に残っている。以来、クラシック音楽は私の友達となった。
マントン DESOLATIONとCONSOLATION
ある年の春、フランス・カンヌを訪れた際に、どうしてもマントンの町に行きたいという衝動にかられて列車に乗った。マントンはカンヌから東に2時間ほどの所にある。すぐそこはイタリア国境。同じく地中海に面しているのだが、溢れんばかりの輝く光で海の色が違っていた。そしてその光の中で古く美しい町並みを歩いた。それにしても自分は、なぜその衝動にかられたのか?マントンという町自体に行きたかったのか、それともその町への列車に乗りたかったのか? その理由はまちがいなく両方だったように思う。

森有正の「バビロンの流れのほとりにて」は、大学入学の頃に購入した古い本だ。序章は氏がパリ発の夜行列車に乗って南仏を旅するところから始まり、最初にマントンを訪れる。その本の通奏低音となっている言葉に、DESOLATIONとCONSOLATIONがある。「悲しみと心の慰め」だ。この言葉は、氏が戦後初めてのフランス政府給費留学生としてフランスを訪れて以来、ヨーロッパにどう向き合うかについて苦悩した中で感じたもので、マントンへの列車の中や滞在した宿での記述に再々登場する。
森氏は、それを「人間が虚しくあるいは無心になってそれを透き通して自然が見えるようになるときに感じられる、ひとつの感情あるいは感覚」という。哲学でも宗教でもないともいう。そのことに気づいてから、知識の上でフランスをもっと複雑に知ろうと気持ちがなくなったとも書いている。文明との対話とは、知的解析しようとする姿勢だけでなく、とにかく無心で接する余裕が必要であることを伝えている。氏は幼い時からフランス語を学び大学院卒業後は各大学でフランス思想史や哲学史を講義したフランス通なのに、ヨーロッパの文明は手強かった事が伝わって来る。
この本は、必ずしも音楽に言及してはいないのだが、音楽を聴くたびにこのふたつの言葉がいつも思い出される。音楽に素人の自分は、解析や批評は置いておいて、とにかく数多くの楽曲を心で聞くことだと観念したら、一層音楽が身近になった。氏はオルガン奏者として国内外で活躍した。そして思想家としての著述はヨーロッパの旅を通じての物が多い。本棚に残っていた古い本書は昭和45年出版とある。DESOLATIONとCONSOLATIONは、その後の音楽を聴いたりヨーロッパを考える際に少なからず支えとなった言葉である。
ベートーベンピアノソナタ 第31番