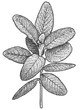top of page
ずっと気になっていた本居宣長(もとおりのりなが)
家の書棚に本居宣長全集が残されている。宣長の肖像の掛け軸がある。そして宣長が仕事に疲れたときに愛用した鈴のイミテーションがある。本居宣長は父親が崇敬した江戸時代の日本古典研究家であり学者なのだ。
宣長は、1730年に伊勢松阪に生まれて1801年に同じ松阪で亡くなった。生業は医師。宣長が生きたのは、徳川8代将軍吉宗から11代家斉にかけての時代にあたる。彼の時代、1774年には杉田玄白の解体新書が出版された。1778年、ロシア船が蝦夷地厚岸(あっけし)に来航。1783年からは何年にもわたり諸国で大飢饉が続いた。アメリカでは1775年に独立戦争が始まり、翌1776年に独立宣言がされた。モーツァルトは宣長より後の1756年に生まれて宣長より早くの1791年に死んだ。1789年にはフランス革命が起きた。そうした内外の動きのなかで宣長は松阪で静かに、医師の仕事をし古事記と向かい続けた。
実は、自分は長らく宣長を敬して遠ざけていた。宣長だけではない。日本の古典や国史関係の書は遠い存在だった。最大の理由は古文書が読めなかったからだ。研究書もうまく読み込めなかった。これは多くの古典研究書が長い専門性の履歴の上に構築されたものなので、語彙の定義がされていないため素人には歯が立たなかったのが実情だ。また、研究者の書いている文章は、その作法が現代の日本語論理展開とは違っていたので、その文章は「判じ物」のようだった。つまりは国史・古典とは「黴(かび)たような文書」という偏見のような思いもあった。
しかし、家の書籍の断捨離作業の中で、宣長はどうも気になって残っていた。このたび思い立って松阪を訪ねることにした。
松阪への旅
2019年10月7日、朝7時半東京駅発の新幹線に乗車し9時過ぎに名古屋駅到着。ホームにある立ち食いスタンドできしめんをすする。これは新幹線で名古屋駅に乗り降りする際の毎回の慣習だ。そして紀勢線・快速三重号に乗りかえて松阪へ。11時前に到着。もう数えきれないぐらいに松阪駅を通過してきたが、降車して市内を巡るのは初めて。バスで松阪城跡公園へ。松阪城址には切り立つような石垣が残されておりその石垣の縁の上を歩くと不安感を��覚えるほどだった。本居宣長記念館は、その城跡公園の傍らに静かにたたずんでいた。




記念館での刺激的な体験
今回の目的は、古事記傳の実物を目の当たりにする事だった。家にある宣長全集は活字で組まれており読み易いのだが、その筆遣いや墨の色や紙の手触り感などが伝わって来ない。宣長が35年間もの歳月を費やし心血を注いで完成した労作を皮膚感覚で接したいというのがねらいだった。また、古事記傳の写真をWEBサイトに掲載するにあたり、その申請手続きでお世話になった学芸員の方にひとことご挨拶したいということもあった。
宣長記念館に保存されている古事記傳は、「再稿本」と呼ばれているもので全44巻。1798年に書き終わった。宣長が亡くなる3年前の事だった。
.jpg)

Copyright Protected
宣長って、理科系か?
「古事記傳三之巻 神代一之巻」の第一ページを見たときに驚いて目を見張った。一文字一文字が、丁寧でかっちりとした楷書体で大きく書いてある。草書体で書かれていると思っていただけに、それは驚きだった。しかも、「カミヨノハジメノマキ アメツチノハジメノトキ‥」とカタカナのルビが漢字の右にきれいに小さく配置されている。これにより、江戸時代の人々は初めて古事記を読めるようになった。そして現代の私たちも、今、大人も子どもも古事記が読めるのだ。私は、吸い込まれるように一文字一文字を追った。
それを見ているうちに、ある想念が頭をよぎった。それは「宣長は理数系の頭脳の人ではないか?」というものだった。
それは、第一に最終的にどんな本にするのか、当初に緻密で精密なデザイン力(設計図)がなければできないというものだ。
また宣長は、古事記を読み解くにあたり、咬合(こうごう、きょうごう)という手法で、古事記のひとつをテキストにして、古事記にまつわる諸文書を比較検討したそうだ。出だしの、「天地(アメツチノ)」の読解だけで、5年もの歳月を要したという。それには、とても長い時間と忍耐力が必要で、なんだか天文学者の観測と記録作業を連想した。
後で知ったことだが、宣長は18歳前後のときに、生活の知恵をまとめた「万覚」(よろずおぼえ)を書いた。そのなかに、いくつかの算数の問題を作成している。
また、17歳の時に、大日本天下四海画図(だいにほんてんかしかいがず)を作った。
これは写本なのだが、畳一畳の大きさの地図にびっしりと書き込まれた地名から、作成時のエネルギーが伝わって来る。
.jpg)
自分が書いた文章を次世代にどう伝えるか?
頭をよぎったふたつめは、調べた事を、人々にどう伝えるかという工夫である。
宣長は、江戸期の人々に古事記傳を読んで貰うために心を砕いた。そのために、現代の我々でも読める、大きな丁寧な楷書体で書き、それにルビをふり本文を読んで貰い、そして別ページで、言葉の背景について註釈をつけた。それは、自分の調査した内容や文章を、どうしたら次世代に残せるか、読んで貰えるかを必死に考えて結果である。結果的に現代まで読み継がれる高度の修辞学であると思われた。この手法はまた、現代の古典・歴史研究書の叙述手法にもつながっている。
そしてこの手法は、近年では、物理学者垣花秀武氏の「奇会白石とシドッチ」や,医学博士で日本の分子人類学者、江戸の骨は語る」(篠田謙一・岩波書店)で顕著である。両者とも、自分が疑問に思った用語について、自分の整理のために基本の定義を丁寧にひもといている。結果として、歴史に詳しくない人びとにとっても、すう~っと伝わって来る。
小林秀雄は、本居宣長(新潮社・昭和52年刊)の読者へのメッセージで、次のように書いている。
「この誠実な思想家は、いわば自分の身の丈にしっくり合った思想しか決して語らなかった。その思想は知的に構成されてはいるが、また、生活感情に染められた文体でしか表現出来ぬものでもあった。」
つまり、宣長は自分が調べた事実を推測や妄想を加えることなくfactとして書いたのだ。この文章は、小林にしては珍しく素直なものと感じられ、ストンと胸に入って来た。
古事記傳を見つめながら、自分も、次世代に理解して貰えるよう、古い漢字は使わず、ひらがなとカタカナのバランスをとりながら、抑え気味で簡潔な文章表現の努力を続けなければと思いながら記念館を出た。そして鈴の屋を訪問した。濃密な3時間だった。
bottom of page