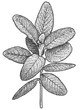倉の片隅から、ひとつの木箱が登場した。箱書きには、嘉永7年霜月に九鬼浦に打ち上げられた大法螺貝(おおほらがい)とある。
嘉永7年(西暦1854年)の秋、霜月4日(旧暦11月、新暦12月)に大地震と津波が九鬼を襲った。ペリー艦隊が二回目の来航を果たし、3月に日米和親条約が締結された年だ。
曾祖父・九鬼閑斎は、災害の直後、九鬼の海岸に打ち上げられた大きな貝を拾った。それを木箱に入れて保存したのである。
嘉永の大地震・大津波を記録した貴重な郷土資料と思われて興味深い。
実は、この年の11月には大地震が日本列島を襲っている。
4日には、駿河・遠江・伊豆・相模に大地震が発生。倒壊流出8300戸、死者1万人。翌5日には、伊勢湾から九州東部にかけて大地震。1万戸が倒壊し、東海道交通途絶とある。(岩波書店 近代日本総合年表より。)
さて、一方で、曾祖父が拾った貝は、大サザエではないかという意見や、ヤコウガイか、また別の貝ではないかという意見もあるので、専門家の意見を聞きたいところである。
歴史的には九鬼浦はたびたび津波に襲われている。
中和一由遺稿集第一巻には、九鬼家第13代九鬼豊隆(1658-1733)の
豊隆一代記に基づいた、次のような記述がある。
■延宝4年(1676)
十月九日津波あり。海水、助三郎の前まで上る。早田浦(はいだうら)
浜辺の家流出。
■元禄一六年(1703)
霜月二十三日丑の刻(午前二時)津波が押し寄せ、助三郎の家まで上り、
早田では十六軒流出、仁木島では逢瀬橋が流出した。
■宝永四年(1707)
十月四日、午の上刻(午前零時)より申の刻(午後四時)まで大地震、
午下刻(午後一時)より津波となり、海水が清四郎(日高屋)の後の階段
まで、久太郎の神棚までも上がった。(中略)清四郎・又三郎・惣五郎・
吉作の新田が悉く流された。家数64軒、舟5艘、網5帖が流出した。
百姓彦兵衛の女房が山で死んだほかは、地下人(村民)は皆無事だった。
尾鷲村では、850余軒が流出し、死人2700余人で、大庄屋小門与助全家族が
流死した。
また宮崎嘉助の日記には次の記述がある。
■昭和19年(1944)12月7日 東海大地震、本宅・海岸の店舗共に津波の大被害を受ける。