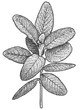断捨離は本から。とはいうものの‥ (2018年6月19日)
もうあと1年あまりで70歳。身の回りの品々の断捨離が急速な課題として浮上してきた。
しかし家には物が集積していて途方にくれる。そこでまず本や雑誌、書類から始める事に。
歴史学者だった父の本と自分が買い求めた本がいま東京の小さな家の本棚15本ほど同居している。庭の物置には段ボール箱が山積みだ。かつて3トンほど処分したのだがちっとも減った感じがしない。知り合いは読んだ本を次々にくれるので寝床の周りも本だらけ。
本には寿命がある。本は湿気を吸い黴と虫食いで物理的にだめになる。研究書や論文はそれを基に若手研究者が新しい研究書を書くのでその使命を果たし終える。そして翻訳書は新訳が出版されてどんどん読み易くなる。
そこで覚悟を決めて断捨離に着手しようと考え始めた。そこでまず手元の何冊かを手に取ってみた。
■「津軽百年食堂」(森沢明・小学館) (6月19日)
生まれ育った弘前市内の地名やら、「津軽そば」の古い思い出が以前にも増して深く心に飛び込んで来た。市井の人びとを取材し、その心を温かく描いた小説。書棚に戻す。断捨離失敗。
■「教養としてのテクノロジー」(伊藤穣一・NHK出版) (6月19日)
かつて一緒に仕事をしたK君がコーディネートして出版したもの。仮想通貨・ブロックチェーンから始めていたので、フロー系の本と思われたが、読み進むうちに、現在のデジタル社会の引き起こす変化を日本人が丁寧に考えなければ、世界から後れを取ることが分かりやすくひもとかれていて、考えさせられた。断捨離失敗。書棚に戻す。
■江戸の骨は語る」(篠田謙一・岩波書店) (6月19日)
江戸切支丹屋敷から出土した3体の遺骨をDNA分析して、そのひとつが、宣教師シドッチの物であることを確認し、復顔するまでの経緯を辿った書。氏は分子人類学の専門家で医学博士。DNA分析の下りは詳細すぎて素人には辟易気味だったが、読んでつくづく感心するのは、歴史に関心を持つ理科系の人々は、基本的な言葉のひとつひとつを丁寧に反芻しながら定義しひもといてゆくことだ。その結果、読者はすぅ~っと理解が進む。
本書を読んで連想し本棚から取り出したのは、「奇会新井白石とシドティ」(垣花秀武・講談社)である。垣花氏も物理学者である。その出だしは、「浪人」を使うか「牢人」を使うかという吟味から始まる。こうした事は文科系の書物や論文では説明がされないか、せいぜい脚注に一行乗る程度。書き手としては、そんなことは常識であり知らないのは勉強不足という事なのだろうが、素人は取り残されてしまう。次世代の人々の理解を進めるということでは重要な事と思う。2冊の断捨離失敗。書棚に戻す。
■これでは本の断捨離は進まない!! (6月26日)
読みだすと懐かしく一層の愛着が湧くので手放せなくなってしまう。
あらためて、本を大きくフロー系(実用書、ハウトゥー本、技術書、語学書、版を重ねている辞典など)とストック系(古典)の大きなふたつにわけて、まずフロー系から捨てることを算段することにしてみた。しかし… それも、そう簡単には行くものだろうか。