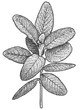top of page
KUKI
tsugaru

世界史潜望鏡


世界史小型機探査
ヨーロッパの略奪再読
2018年6月28日
イタリアの難民対応とポピュリズム
2018年6月28日
メルケル首相 EUリーダーの苦悩
2018年6月28日
音楽
音楽
・ベートーベン 交響曲第8番 第2楽章
・マントン
・ベートーベン ピアノソナタ31番
・シャコンヌ
・BWV998
津軽
弘前公園西濠の夜桜(弘前公園総合情報サイトより)
大学紛争の新聞記事
2018年12月6日

ひきだしから、一枚の古い新聞記事が出て来た。
昭和44年(1969年)9月のものである。弘前大学からの求めにより、機動隊がキャンパスに入り、学生による3週間に亘る大学本部封鎖を解除したというもの。
この年は、1月に東大安田講堂事件があり入試が中止となって受験生は大学選びで混乱した。自分もその一人だ。その後、全国的に大学紛争の嵐が吹き荒れた。争点のひとつは大学の自治とは何かである。私の進学した大学も開店休業状態。将来が見通せずひどく困惑したことを覚えている。
大学紛争はこの年の暮れ近くから急速にトーンダウンした。ただ学生運動そのものは大学キャンパスから学外に移り、いくつもの社会事件が起きた。今も一部で激しい活動が続いている。
それから40年以上が経った2011年1月、東京の通勤電車内で、若手サラリーマンが読んでいた少年マガジンの裏表紙に弘前大学のPRが眼に入った。この広告を見た男女はどんな思いで弘前での大学生活を送る事になったのだろうか?時代の移ろいに感慨深いものがあった。

久々の弘前
2018年11月6日
母方の最後の叔父が亡くなり葬儀参列のため久々に弘前を訪れる。葬儀の合間を縫って銅屋町にある最勝院を訪問。ここは自分が育った家の近所にあり、父母は幼いこどもを連れて境内でお重の弁当を食べた。境内にある五重の塔内の暗く急な梯子をつたって何度か登った。その一番上の扉を開けたとき、その向こうに見えた風景は何だったろう。記憶を辿ると高い木々の間から緑の平野が遠望されたことを覚えている。
境内で記憶に残るのは、三十三観音だ。小学校に上がってからは毎日その境内を通って通学した。未舗装の裸土に並ぶ鼻のかけた観音像たちを両脇に見ながら通ったことを思い出す。
当時と違い、五重塔も境内も観音も綺麗に修復整備されて見違えるようになった。訪問時に、近所の幼稚園児に遭遇。遊んでいる姿に幼い自分の懐かしい記憶が蘇った。




太宰治の「津軽」の旅
2018年6月28日
これは12年前の古い旅の記憶。津軽半島をゆっくり旅することが長年の課題だった。弘前で生まれ育ったのに津軽半島には小学校の臨海学校で三厩(みんまや)に一度行ったきり。
旅をしなかった訳は、とにかく交通不便だったからだ。また同じ津軽に暮らしていても津軽半島付近の言葉は多様で何を話しているかわからない事がままあった。少年時代には、津軽半島付近は津軽弁で「あがじゃご」(赤在郷、つまり、ど田舎)と感じてもいた。本当にそうなのか? それで、津軽半島の車の旅に出たのが12年前。その結果、目から鱗が落ちる事が次々と目の前に登場した。背景には、太宰治の「津軽」があった。
白神山地




白神山地のビジターセンターで、「ここから林道を車で走って西海岸の深浦に行きたい」と話したら、担当者は「止めた方が良い」と真顔で言った。林道は整備されておらず事故が起きた際に立ち往生する。しかも携帯の圏外で助けが呼べないというのである。しかしブナの原生林の中に身を置きたいと願った私は折角の忠告をありがたく聞きながらも、あえて車を林道にいれた。
そこは別世界だった。誰一人いない。後続車も対向車も来ない。ブナは森の女王とも呼ばれている。ブナの広葉樹独特の柔らかな緑と夏の光に体ごとくるまれて酔うようだった。ときどき車を止めて多くの写真を撮った。
津軽の豊かな自然を再発見した忘れえぬ風景だ。
斜陽館と母の実家
2018年6月28日

金木町(かなぎまち)の斜陽館に初めて足を踏み入れた時、なんとも言えない懐かしさに襲われた。一階の土間と上がり框(がまち)のたたずまいが、母の実家に良く似ていたからだ。
斜陽館の入口は建物の大きさに比して狭いのだが、そこを通ると奥深くまで土間が広がっている。そこは農作物や荷物、荷車の置き場である。土間の左に沿って上がり框(あがりかまち)が長く続いている。そこで履物を脱いで上がると、また広い座敷がいくつも並んでいる。一階に座敷は11もあるそうだ。座敷の奥には細密な彫金をほどこした超豪華な仏壇がある。2階には洋間がいくつも作られた。斜陽館を建てた太宰の父・津島源右衛門は大地主。保有水田は200町歩(ヘクタール)とも250町歩ともいわれ、その水田は豊かな米を産んだ。金木周辺は豊饒の土地だったのだ。棟梁は明治時代の堀江佐吉。今も弘前に残る数々の洋風歴史建築を手がけた人だ。

私の母の実家・竹内家は、弘前中央部の中土手町で150年間に亘り味噌・醤油の醸造工場を営んでいた。入口から見た土間と座敷の位置関係は斜陽館とは左右対称だったけれど、建築デザインの考え方は同じ。土間には、リヤカーや自動車、出荷物が置かれていた。土間は奥深くまで続いていて、工場の巨大な桶がいくつも並んでいた。私たちは上がり框で靴を脱いで座敷に上がった。奥にはやはり仏間があり、祖母が燈明のもと、ご飯を供えて祈りを捧げる姿があった。正月には多くの親戚が座敷に集まった。嫁に出た母と私たち家族にも声がかかり、正月のごちそうにあずかった。寒ブリの刺身が朱塗りのお重の中に並んでいて子供の目にもたいそう美しくおいしいものだった。従兄が工場の広い屋根でスキーをしていたのが印象的だった。
夏には2階から目の前の大通りを次々にねぷたが通ってゆくのが見えた。扇型のねぷたの前面には首がはねられ血しぶきが飛ぶ恐ろしい戦いの姿に圧倒された。裏側の見返えり絵の美女が幽霊のようで怖かった。そして空気を震わす大太鼓に、恐怖感に締め付けられながら夏祭りが心に刻まれた。実家が堀江佐吉翁に関係しているのかどうかについては良くわからない。雪に強い東北伝統の職住が組み合わされた町屋のつくりかたが踏襲されていたのかもしれない。その建物は今はもう取り壊された。
斜陽館で気になったのは、広い多くの座敷の中で、こどもたちは一階の一角にある狭い畳部屋に押し込められていたことだ。子供たちにとっても一緒にいた方が寂しくなく温かだったのかも知れないが、一方で子供部屋の中で兄弟の格差や確執もあったに違いない。また、日常はおばと女中「たけ」が世話をした。その複雑な環境の中で太宰はその部屋で何をどう感じて育っていったのだろうか。太宰は、やがて金木を出て青森中学、そして弘前高校に進学した。

蟹田駅のこと
2018年6月28日
記事準備中
津軽の興味深い言葉
私は弘前生まれ。幼児から高校卒業まで津軽弁にどっぷり浸かって暮らした。
津軽を離れてもう50年以上になるが、ふと思い出されて来る言葉がある。
それらは、懐かしいというよりも、興味深く、ある意味ではユニークでキテレツで、思い出すと思わずニヤリとするような言葉たちである。
代表的な言葉として「ワイハ!」がある。母や親せきの中年女性が良くつかっていたもので「まあ驚いた!」という意味だが、男の子はあまり使わなかったので聞く度に笑い、特に強烈な印象として残っている。
■小学校時代に女の子が使っていた、特に面白かったふたつの言葉
・アリータリ! (あれ~あれ~)→ 人の失敗を揶揄することば
・モチョクチャイ!(くすぐったい)
■津軽弁の特徴のひとつに、助詞による表現の多様性があるのではないかと思う
例えば、「YES、そうだ」という時の中立的表現は、「んだ!」であるが…。
んだな! → (そうだな) 強調する時に、男性が使う事が多い。
んだきゃ! → (そうよそうよ) 若い女性が使う事が多い。
んだねは! → (そうよね) 中年女性が使う事が多い。
んだねし! → (そうよね) 中年女性が使う事が多い。中年男性も。
んだずな! → (そうだな) 中年男性が使う事が多い。
んだびょん!→ (そうかも知れない)年代男女を問わず使う。
最後の「んだびょん!」は、会話の中では、「んだびょ~ん!」や、「んだびよ~ん!」に
細かく変化したので、特に興味深く印象に残っている。
■津軽弁は、奈良時代の言葉が全国に同心円状に全国に広がった結果だと、ものの本で読んだことがある。
そして往時は、地域間の人の往来が限られていたため各地に方言が形成された。
津軽弁は、青森県西部の各地で訛りに大きな違いがある。また、口を大きく開けないで早口なので良く
わからない事も多かった。実際、弘前の私の自宅の隣のおばあちゃんの津軽弁は、子供時代から高校を卒業するまで理解できなかった。
こんなことを東京で話すと、人々は「目くそが鼻くそを笑っている」と反応する。でも事実なのだ。
ところで、津軽の人々は、現在、津軽弁と東京言葉の完全バイリンガルである。
音楽
GLOBE
Copyright Protected
世界

これは家に残るヨハン・ブラウによる世界地図。もともと1648年にオランダで作られた。時代は三代将軍徳川家光後期。長崎に出島が建設されてから12年後のこと。世界は急速に小さくなり幕府の舵取りが難しくなった。2019年現在、世界の構造はますます複雑化している。その世界の現在を垣間見る。
ジョンソン首相のイギリス(1 )
2019年12月28日
イギリスはEU離脱に向けて時間がない。2020年1月末に離脱したのち、移行のための条件整備を2020年12月末までにEUと詰めなければない。日本のメディアは、関税や国境管理、移民と人の移動など、イギリスの経済と政治構造はどうなるのかについて日々、動き伝えている。しかし見ても読んでもわからない事ばかりだ。
英国民の気持ちや離脱後のイギリスの将来ビジョンが見えてこないのだ。
結局、自分はイギリスという国については知っているようで知らな過ぎる事に気がついた。
学生時代には英国の歴史を学習し、何度か旅をした。BBCニュースも見て来たのに…
情報へのアプローチの仕方が、表層的だったのか…
人びとは英国にどんなアイデンティを持っているのか?
そこで、現在のイギリスとは何かを今一度はじめから復習することにした。70歳の手習い。

その手始めは、イギリス総選挙で圧勝した保守党ボリス・ジョンソン氏の2019年12月13日の首相官邸前の勝利宣言スピーチの聞き直しだ。
勝利宣言は実に簡潔なものだった。その表現はふたつの特徴を持っているように思えた。
第一は、ジョンソン氏が「国民」と「国」という用語についてシンプルな言葉を使っていること。
国民をpeopleと表現したのが11回ある。そのうち、people of this countryが2回、British people が2回。
peopleは、一般的表現であるとはいえ、そもそも多民族が住むこの国の人びとに結束を呼び掛けるためにだれにもわかる用語選択を選択したのではなかったのかと推測する。
国民は、nationと公式的に表現されるのが多いのだが、今回の勝利宣言ではスピーチのしめくくりに僅かに一度、as the nation hands us the historic mandate (国民は私たち保守党に歴史的課題を託したので…)という文だけだった。
「国」をcountryと表現していることも興味深かった。総計5回使われている(上記の2回を含む)。
イギリスには、かつてはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4王国があった。それを統一して作り上げた現在の国名は、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 )。だが、「連合王国」という名称使用も、ジョンソン氏は積極的ではなかったと思われた。United KingdomやUKは、それぞれ1回ずつだった。
第二は、実にシンプルな時制(tense)を使っていることだ。
スピーチには現在形とwill(未来形、そして意志を示す)しか見られない。過去形もなければ現在完了形も過去完了もない。関係節はthatを使うものが数えるほどしかない。これは、スピーチが単文節でダイレクトに聞き手に伝わってくる。若者にも移民にもそして日本人にもわかりやすい。さて英語を母国語にする大人にはどのように聞こえていたのだろう。
ただし…
同年9月24日の国連スピーチ内で、ボリス氏は、関係節と現在完了形を多用しており文体が全く違う。役人が書いたのだろうか?使い分けたのだろうか?
乱暴な言動が目立つジョンソン氏だけれど、勝利スピーチ表現からは注意深さも感じられた。そして、その反面、最終的な国と国民のありようについては、その詳細がまだ明確になっていないようにも思われた。
以下次号。
【補足】
イギリス経済は19世紀末から長期低落傾向を見せ始めた。第二次世界大戦後にヨーロッパで形成されて来た各種の経済共同体との連携を模索したが成功して来たとは言えないだろう。EEC,ECなどですったもんだがあった。EFTAはうまくいかなかった。最後にEUに加盟した。そして、EU離脱へ。一連の動きの底辺にあるものは、何か?
大英帝国と国民が持ってきた自負なのか?
イギリスは島国で大陸とは地続きでない事が大きな特徴だ。これは日本と同じ。
大陸との間には「ドーバーの白い崖(White Cliffs of Dover)」があり、昔々から外敵の攻撃が難しかった。だからイギリスは、過去の成功経験に戻りもういちど自国完結型で国を運営してうまくゆく道をとりたいし、とれると考えているのだろうか。金融の中心地、シチーはその存在をどのように維持し続けようとしているのか?
すでにイギリスはEUに加盟しユーロトンネルを通って大陸との間で多くの人々とモノが行き来している。世界からの移民も国内各地に住み三世となっている。かつての4王国が抱える軋轢だけでなく移民問題により、国民のアイデンティとは何かが、よりあいまいで複雑になり顕在化しているように見える。
キーワードは、国と国民のアイデンティではないだろうかと思える。そして、根底にある心とは?
2018年6月28日
記事準備中
魔物としてのアメリカ
2018年6月28日
記事準備中
メルケル首相のドイツ
2018年6月28日
記事準備中
「ヨーロッパの略奪」再読
記事準備中
bottom of page